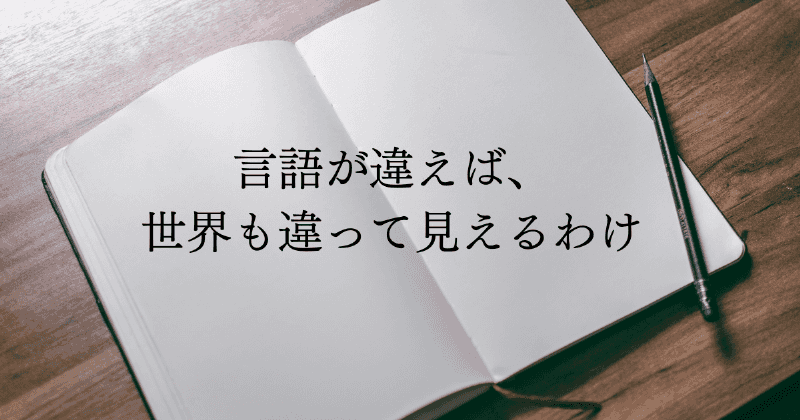『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』を読みました。英検1級過去問の長文読解問題を勉強していて知ったのですが、想像以上に色彩と言語の話に多くのページが割かれていたので、こちらでも紹介します。
本書の内容をもっとも端的に表しているのではないかと思えるレビューがこちら。
英国ケンブリッジ大学で言語学を研究する著者が、言語を異にする人間は世界の認識方法も異なるという、いわゆる「サピア=ウォーフの仮説」の流れをくむ言語相対論は真正か否かについて、2000年代にまで及ぶ近年の研究を丹念に追いながら論じた一冊です。
「表しているのではないか」というのは、正直、言語相対論のことは難しくてよく分からなかったから。
がっつり取り組むつもりで読み始めましたが、途中で挫折しそうになったので、頭がきれる人が非常に魅力的な語り口で、人間の色の認識について、難しいけどとても面白い話をしてくれているのを聞いている、というモードに切り替え、最後まで目を通しました。
色の認識については、色々な仮説があったといいます。19世紀には、色彩についての語彙が乏しい=見分けられる色が少ないとされていたようです。
例えば、ホメロスの抒情詩において、海が葡萄酒色、蜂蜜が緑と表現されたり「青」にあたる表現が全く見当たらなかったりするのは、古代人が色弱だったからではないか?
その後人間の色覚が進化したのではないか?
などなど。
しかし、色覚検査をしてみると、現在も多くの色名を持たない民族の人々も豊富な色名を持つ人々と同じように色の差を見分けることができるといいます。色の語彙が少ないのは見分けられる色が少ないからだ、とは言えなさそうです。
面白かったのは、著者ドイッチャー氏の「味」を色になぞらえた思考実験(94ページより)。
今から遠い未来に、どのような味や口当たりを持つ果物でも作れるというマシンが開発され、私たちの子孫は、味と口当たりについての語彙を何百も発達させているという世界の話です。
原始文化を専門とする人類学者がシリコンバレーの原住民のもとへ急いでいると思ってほしい。シリコンバレーでは暮らし方がグーグル時代から1キロバイトも進歩しておらず、道具も21世紀そのままの素朴さだ。人類学者はマンセル色見本ならぬマンセル味見本を携えている。
(中略)
人類学者は原住民に、ひとつずつ試してみて、原住民の言葉で味をなんというか教えてほしいと頼むが、彼らの果実に関する語彙の乏しさにびっくりする。
(中略)
ひょっとしたら、彼らの味蕾はまだ進化途上ではないのか。しかし、原住民を検査したところ、味見本のなかのどのふたつをとっても、区別できることがわかった。味蕾におかしなところはない。では、なぜ彼らの言語は欠陥だらけなのか。
(言語が違えば、世界も違って見えるわけより)
「マンセル味見本」という言い方は面白いですね。
そして確かに、現代の私たちの味の語彙は色の語彙に比べて乏しいのです。せいぜい「甘い」「酸っぱい」とか「○○に似てる」ぐらいで。
しかし、私も含めて多くの人は、それで不自由を感じていません。社会が違えば、色もそうだというだけの話です。
なお、本書には、カラーコーディネーターや色彩検定受験者にはおなじみの、バーリンとケイも登場します。色彩の勉強をしている人はぜひご一読。