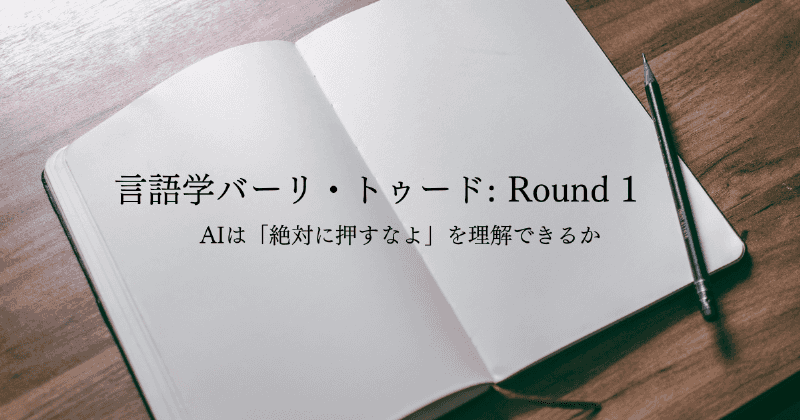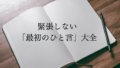言語学者の川添愛さんの「言語学バーリ・トゥード: Round 1 AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか」を読んだので、その感想です。
本書を知ったきっかけは、大岡玲さんの「一冊に名著一〇〇冊が詰まった凄い本」でした。
サブタイトルの「絶対に押すなよ」はダチョウ倶楽部のネタのひとつです。熱湯風呂コントで、上島竜兵さんにこれを言われた肥後克広さんや寺門ジモンさんは、上島さんを熱湯に突き落とすことになっていました。
すなわちそこでの「絶対に押すなよ」は「押してもいいよ」と同義。言葉の意味とは正反対なわけで、なるほどこれをAIに教えるのは難しそうだなあ、言語学者はどう考えているのだろう?と興味を持ったわけです。
ただ、一冊を全部読み通せるかというのは、自信のないところでした。タイトルの「バーリ・トゥード」は格闘技の一類型の名称であり、著者の川添愛さんは格闘技ファンだというのです。
私の格闘技の知識は「緑の毒霧」「人間山脈」「鉄の爪アイアンクロー」などの単語が断片的に頭に入ったところからほぼアップデートされていないので、面白く読めるかなあと懸念していたのですね。
結論から言いますと、その心配は無用でした。「バーリ・トゥード」はWikiなんかでは「最小限のルールのみに従って素手で戦う格闘技の名称」と説明されますが、ここでは単に「何でもあり」と読み替えて差支えありません。
そしてこの言葉が、私にとっても悩ましいテーマの具体例として使われている回を読んだとき、これは全部読むべき本だろうと確信しました。
そのテーマとは、相手と知識を共有しているかどうかが分からないときにどう話を切り出すか、ということ。「バーリ・トゥード」を知っているかどうかわからない人に、
(1)私、バーリ・トゥードの試合を見てみたいんだ。あれ、生で見たらすごいと思うよ。
と言うのが適切かどうかの問題です。
日本語の場合、(1)のように専門用語や固有名詞をそのまま何もつけずに「裸で」言い、とくに補足説明もしない場合、「それが自分と相手の共通の知識の中に含まれている」という話し手の思いが表面化することになる。
この場合の話し手の思いを、筆者は「自分の知っていることは相手も知っていて当然」とも説明しています。相手がその専門用語や固有名詞を知らない場合、ずいぶん傲慢な人だなあという印象を受けるかもしれません。
そのような悪印象を避けるためには、相手が「バーリ・トゥード」を知っているかどうかを探ってから話を切り出す必要がありますが、これが実に難しい。というのは、知っているけど知っていることを他人に知られたくないという場合もありうるからです。
では、次のように「という」を付けたり、説明を加えたりするのが無難かというとそうでもなく。
(1)私、バーリ・トゥードというスタイルの格闘技の試合を見に行きたいんだ。それは<これこれこういう(説明)>ものなんだよ。それを生で見たらすごいと思うよ。
これだと、相手が「バーリ・トゥード」を知っている場合には、「知っとるわ!」と憤慨されるかもしれません。難しい。
そういえば昔、大学の後輩と音楽の話をしていて、「最近ジャニス・ジョプリンという人のアルバムをよく聴いている」という趣旨のことを言ったところ、「それぐらい誰でも知ってますよ」とムッとされたことがありました。
日本のハードコアパンクが好きな若者だったので、いわゆるクラシック・ロックは知らないかもしれないと思い、いちおう配慮をしてみたのですがプライドを傷つけてしまったようです。
他方、これまた30年ほど昔、職場の同僚とビートルズの話になったとき、「自分はどちらかと言うとローリング・ストーンズの方が好き」と言って「ローリング・ストーンズ」って誰?と聞き返されたことがありました。
ビートルズvsストーンズという図式を採用していたことの痛さはさておき、当時の自分にはビートルズを知っている人はローリング・ストーンズも知っているだろう、という思い込みがあったんですよね。「ストーンズ」と略さないことで配慮を見せたつもりだったのですが、さじ加減が難しいところだと思いました。
筆者もその点については、誰でもどこかで「相手もこれを知っているという前提で話すべき」か、「相手はこれを知らないという前提で話すべき」のどちらに賭けるかというバクチを打っているはずなのだ、と言っています。
もう一つ、特に印象に残ったのは、「自虐的な発言をする相手にどう対応すべきか」がテーマの回です。
例としてGRAYのTERUさんと氷室京介さんの対談が取り上げられていたのですが、あのヒムロックの「俺はあんまり声がよくないからさ」という自虐発言に、TERUさんはどう答えたのか?
TERUさんの対応については、ぜひ本書をお読みいただきたいのですが、筆者はこの問題について結局は「心」だろうみたいなことを言っています。
なんだその結論は、と一瞬ずっこけたのですが考えてみるとまあそうなのかなあと。なんというか、言葉によるコミュニケーションにおいて「この場面ではこう言えば正解」というマニュアルのようなものはない、ということをあらためて認識させられた1冊でした。
ところで、読書にあたっての私の習性として、著書のことをよく知らずに読み始めることがあるというものがあります。
今回もそのパターンでして、途中で「この川添さんて人は面白いなあ、他にどんな著作があるんだろう」とプロフィールを見てみたところ、すでに読んでとても満足度の高かった「働きたくないイタチと言葉がわかるロボット」の著者だったのでした。納得。